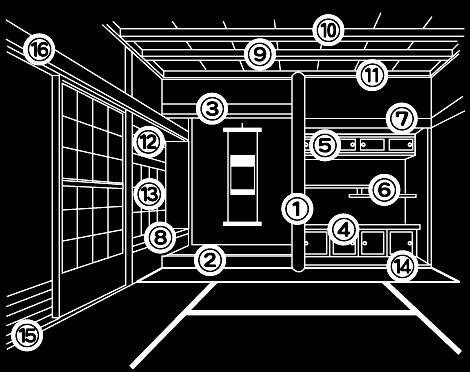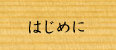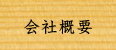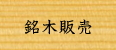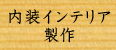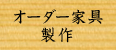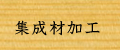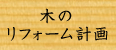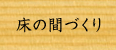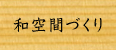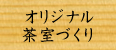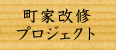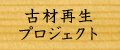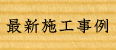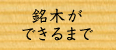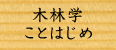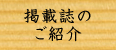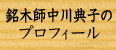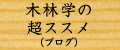幼いころ、祖父に連れられてよく木を見に行った。比叡山の寺につながる林道のスンスンと伸びた杉や檜、中川・細野地方の北山杉、堀川の銀杏、青蓮院の大楠、円山公園の技垂れ桜、賀茂街道の楠と桜並木、今は無いが御地通の欅(けやき)並木などを見ながら歩いた。
木の目利きと呼ばれた祖父は、社寺仏閣や幼い私や妹でも行ける山道を散策するのがお気に入りで、遊びと称して、木に抱きついて木中の音聞きごっこをした。木は生きていて、必ず声を持っている。
雨の日のあとは水を吸い上げる音がサーザー響いた。風にたなびく枝先の音が騒がしくなると急に天気が悪くなったり、風も無く木が静まり返ると、それが雪のまえぶれだったり…。
特に、祖父の残したもので木の生命力を教えられたのが、山陰産の「松の年輪」。十五年ほど前に祖父が見つけてきたもので、当時、創業二百七十年の祝いに合わせて、年輪も約二百八十重ねている。年輪は一年で一つできる。つまり松は二百八十年以上生きていたことになる。
十五年前に一度、八年前にも一度、職人が手カンナをかけて表面を削ったにもかかわらず、いまだに松はジワリと松脂(まつやに)を出している。製材して二十年以上たつ松の生命。
生命ある木を見いだすことは木の文化を知ろうとする、第一歩なのだと語りかけてくれる。
|